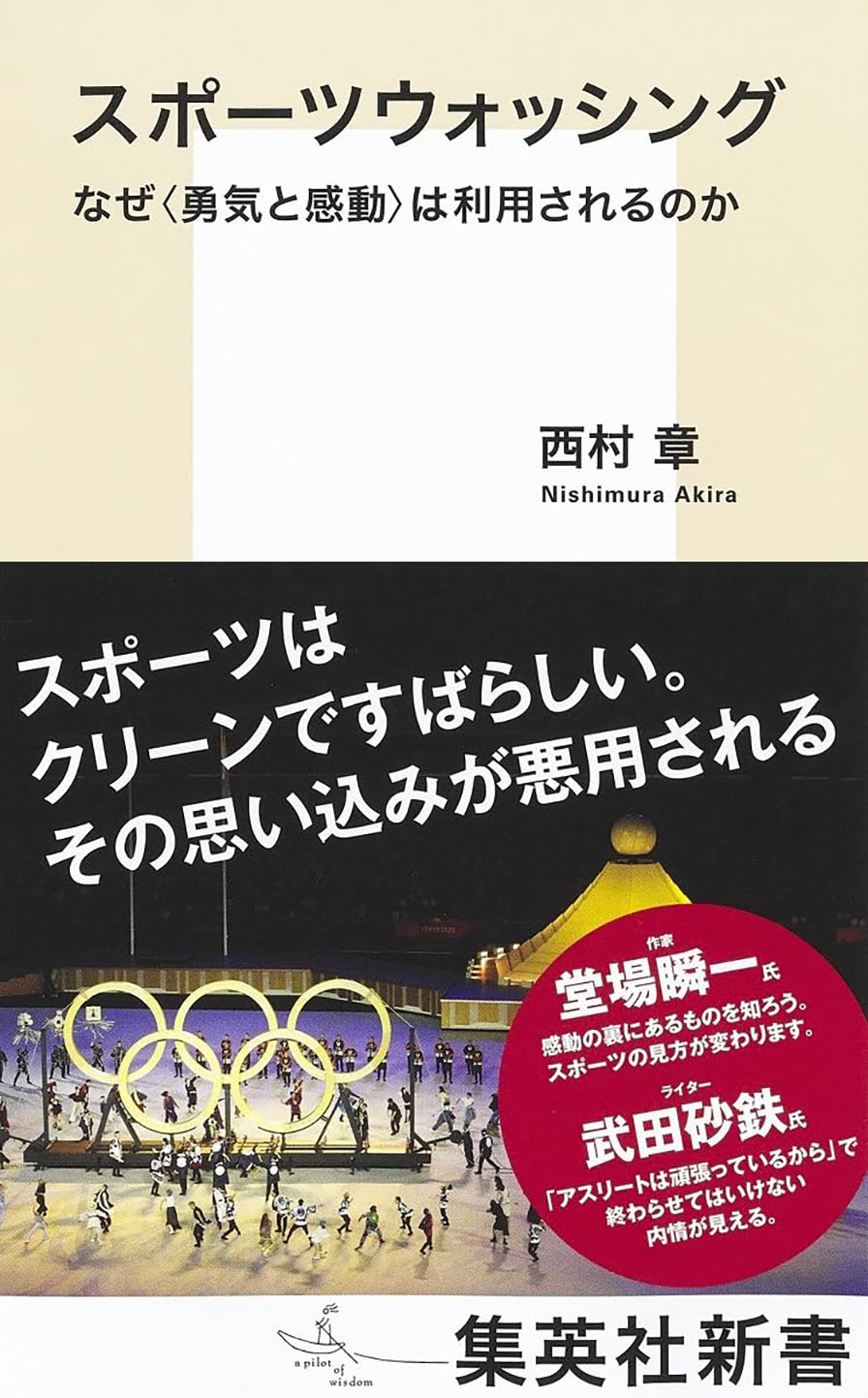●文:西村 章 ●写真:MotoGP.com
早いものでもうシーズンは第11戦、オーストリアGPである。国際映像などからもわかるとおり、開催地のレッドブルリンクは結構な山の中に位置している。近郊にはシュピールベルクやユーテンブルクという小さな街があって、それなりのホテルもあるそうなのだが(そういうところに泊まったことがないのでわからない)、数が少ないそれらの便利なアコモデーションはレースのオーガナイザーやチーム関係者たちにあっという間に占有されてしまう。なので、各国取材陣のほとんどは、サーキットから遠く離れた山間部の民宿やゲストハウスのようなところを探してあちらこちらさまようことになる。幸運に発見した宿がサーキットから50kmで片道1時間程度の距離なら御の字、といったかんじで、オーストリアGPの週末には「どこに泊まっている?」という会話が挨拶代わりにパドックのあちらこちらで交わされるのが通例だ。
そのかわり、といってはなんだが、この会場ではプレスルームの一角に食事のケータリングサービスを行う一角があって、朝昼晩に温かい食事が週末を通してメディアに提供される。さすが砂糖水で世界の市場を席捲する大企業が所有する会場である。あとはここでシャワーを浴びて眠ることができれば文句はないのだけれども、さすがにそこまではムリですね。
そんな当地がカレンダーに復帰したのは2016年。当時は日本メーカー勢、というかホンダとマルク・マルケスの全盛時代で、そこから大きく後れを取っていたドゥカティが、当地久々のレースで勝利を挙げた(2010年オーストラリアGPのC・ストーナー以来6年ぶり)。要するに、ダッリーニャ体制になって初の優勝である。
それまでのレースでも優勝争いを繰り広げたことはあったが、最高でも2位という結果で、表彰台の頂点にはなかなか手が届かなかった。そんな背景事情があって、苦節6年ついにドゥカティ優勝、というじつに感動的なレースだったのだが、その栄誉に浴したのは誰もが想像していたA・ドヴィツィオーゾではなく、チームメイトのA・イアンノーネだったのですね。たしかにめでたいんだけれども、なんかちょっと微妙かも……、という復活劇だったこのときの出来事をご記憶の方もいるだろう。
そんな当時と比べると、いまやメーカー間の形勢はまったく逆転し、現在はドゥカティの黄金時代が続いている。今回のウィークでも土曜スプリントではペコ・バニャイア(Ducati Lenovo Team)が1等賞の金メダル、2等賞の銀メダルはホルヘ・マルティン(Prima Pramac Racing/Ducati)、3等賞の銅メダルにはアレイシ・エスパルガロ(Aprilia Racing)が入った。
バニャイアは日曜午後2時にスタートした決勝レースでも優勝して、2位にマルティン。3位にはドゥカティファクトリーのエネア・バスティアニーニ。というわけで、またしてもドゥカティが表彰台を独占した。前回のレポートでもお伝えしたけれども、第4戦スペインGP以来、決勝レースの表彰台はすべてドゥカティ勢、という状態が続いている。今回で8戦連続24個の連続表彰台である。
ちなみに当地レッドブルリンクの成績はというと、上でも言及した2016年のレース再開以来、2021年のB・ビンダー(KTM)を除きずっとドゥカティ勢が優勝している。その優勝者を列挙してみると、A・イアンノーネ(2016)、A・ドヴィツィオーゾ(2017)、J・ロレンソ(2018)、A・ドヴィツィオーゾ(2019、2020)、B・ビンダー(2021)、F・バニャイア(2022、2023)、という顔ぶれ。
さらに言うと、バニャイアは当地レッドブルリンク3年連続勝利だが、ヘレスとムジェロ、アッセンでも3年連続勝利を達成している。これだけ強いと、彼とドゥカティというコンビネーションの無敵っぷりはいろんな数字になって反映される、というわけだ。
今回の決勝レースでも、バニャイアは圧巻の強さを見せた。中盤周回まではマルティンがコンマ数秒の距離で食い下がっていたものの、じわじわと引き離してゆき、後半にはついに2秒という大きなギャップを開いてしまった。マルティンと後ろのバスティアニーニも4秒ほどのギャップがあり、言ってみれば〈ドゥーハン均衡〉みたいな状態で(すみません、いま作った言葉です)、終盤は表彰台圏内の3選手それぞれが単独でぐるぐる周回を続けてゴールした。
土日ともに完璧なレース運びでシーズン3回目の週末ダブルウィンを達成したバニャイアは
「昨日はホルヘのペナルティ(LLP)もあって少しラッキーな面もあったけれども、今日は本当に最高のペースで走ることができた。自分でもすごいスピードを発揮できたと思う。毎周、ホルヘより少しでも速く走ろうと心がけて、レース終盤にあれだけの差を築くことができた。ストレートではリアがかなり振られたけれど、それもうまくコントロールできた。そこをうまく扱いきるためにも、ギャップを作っておくことは重要だった」
と、まさにレースをコントロールしきった百点満点のコメントである。
いやあ、ドゥカティは強い、ペコはうまい、ということを今さらながら改めて確認させてくれるレースであったことに異論のある人は、おそらく世界じゅうさがしてもほとんどいないのではないだろうか。では、今回のような展開で二輪レースのスリリングな醍醐味を存分に愉しめたのかというと、そこはまあたしかに手に汗握るバトルの面白味、という点では興趣を欠く面は否めないけれども、王者の圧倒的な強さをこれでもかと見せつける危なげのない勝ちっぷりも、ま、たまにはいいものですね。というか、たとえそんな一方的な展開であっても見る者を飽きさせず、むしろ最後までなんとなくずっと惹きつけてしまうのは、バニャイアのいかにも現代風な好青年的魅力が少なからず影響しているのかもしれない。
現代風といえば、目下のところ熾烈にタイトルを争うバニャイアとマルティンは、レースになればコース上での緊張感こそ漂うものの、コース外での厭な牽制合戦や心理戦のようなものは見られない。その関係性について、両者は以下のように述べている。
「相手をリスペクトしていれば、コース上では激しい戦いになってもコース外で平静を保つことができる。だから、要は敬意の問題だと思う。僕とホルヘは幼い頃に知り合って、もうかなりになる。チャンピオンシップで関係性がガラリと変わるような選手たちのことは、まったく理解できない。同じ目標に向かって戦うライバルであることは事実だけど、それでも相手に対して尊敬の念を常に持ち続けることはできる。(マルティンとの)子供時代の関係性が、今も自分の中には残っているんだと思う」(バニャイア)
「ペコの言うとおり、自分たちは去年や今年知り合った間柄じゃない。長い間ずっと、互いにライバルとして戦ってきた。自分が全力を尽くして、それでも相手のほうが上だったとして、その相手をどうして憎まなきゃならない? そこは尊敬するでしょ。コースの中でも外でも敬意を持って接しているから、向こうが勝ったときは素直に祝福できるし、この関係はこれからもずっと生涯続いていくと思う」(マルティン)
ひと昔ふた昔ほど前は、タイトル争いを繰り広げるライダー両名に対して対立を煽りたてるようなメディアの論調も少なくなかったし、それをうまく利用することでライバルたちを精神的に追い込み撃沈してきたのが、バレンティーノ・ロッシという人物だった。そんな彼の戦い方にも毀誉褒貶はいろいろあって、それがまたさらに彼の人気に火をつけたものだが、もはや今はそういう時代ではない、ということなのでありましょう。時代が変わって主役たちも変われば、その関係性が変わってゆくのは当然だし、「ゆく川の流れは絶えずしてしかももとの水にあらず」というのは、まさにこういうことを指すのでしょう。
さて、今回の週末ではチャンピオン争いやレース展開以上に、少なくとも日本人ファン諸兄姉に大きな注目を集めたのが、小椋藍(MT Helmets-MSI)のMotoGP昇格のニュースだ。
しばらく前から囁かれていたとおり、Trackhouse Racing(Aprilia)から2025/26の2年契約で参戦すると発表されたのが木曜日。初日金曜日は午前午後ともトップタイムを記録して小椋は絶好調の走り出しに見えたが、土曜に右手を負傷し、決勝レースは残念ながら欠場することになった。
そのレース結果はともかくとしても、小椋のアプリリア陣営からの昇格決定はいろんな意味で朗報であるといえそうだ。
まずは、”Road to MotoGP”をキャッチフレーズとするアジアタレントカップ(ATC)出身者から初めての最高峰到達ライダーである、ということ。
これは意義深い。小椋が世界の最高峰で戦うことは、ATC出身の他の現役ライダーや、ATCやそれ以外の世界各地域タレントカップに参戦中の若手選手、そして、それらのタレントカップへの参加を検討する少年少女やその保護者たちにとって、大きな励みになるだろうし、目標にもなることはまちがいない。
次に、23歳という年齢。
2019年にMoto3クラスでフル参戦を開始した小椋は、2020年に同クラスのチャンピオン争いをして翌21年にMoto2へ昇格。22年はシーズン最終戦まで熾烈なチャンピオン争いを続けたことは、多くの方がご記憶だろう。そこからさらに2年間の経験を重ね、現在ふたたび同クラスでチャンピオン争いを繰り広げている状態で、23歳という年齢で来シーズンにステップアップを果たす、というタイミングは、拙速でもなく遅すぎることもなく、心身ともに充実した時期の人生の選択であるように見える(ま、外野はいつだって勝手なことを言うわけですが)。
そしてもうひとつ、アプリリアからのステップアップである、ということ。
日本人選手が最高峰クラスに挑戦してきた長い歴史を振り返ると、ホンダやヤマハの育成を経て巣立っていくことが圧倒的に多いため、その育成されてきたメーカー系のチームから参戦を果たすことが長年の通例になってきた。このような参戦のありかたは、パドックではともすれば「日本人枠」と揶揄されることもあるが、たしかに耳の痛い一面の事実ではあるだろう。
今回の小椋は、そのような国籍優位性(とあえて表現するけれども)に頼ることなく、実力を公正に評価されたうえでシートを獲得した、という事実は、チームマネージャーのダビデ・ブリビオの言葉を見れば一目瞭然だ。
小椋の最高峰昇格が発表された木曜夕刻にはブリビオもメディアの取材に応じたが、その際には以下のように述べている。
「いくつかの選択肢がある場合に、どれかひとつを選ぶのはいつだって難しい。我々の場合、最初に直面したのは、ミゲル(・オリベイラ)のままで行くか、あるいはライダーを変えるのか、ということで、ここが一番大変だった。
我々はミゲルになんの不足も不満も感じていなかったし、彼は真面目で、豊かな才能のある偉大な選手だ。ミゲルの能力が今の成績以上のものであることは、いうまでもない。だからそこは悩みに悩んだけれども、今までと別の方向へ行ってみようと決めた。だとすると、進むべき方向は若い才能で新たなプロジェクトを始めることだ。
MotoGPで戦える資質を持った選手、ということならば、それは藍だと我々は考えた。どんな選択であれ容易なものなどない。けれども、選ばなければならない。だから、この方向で行こう、と決定したというわけだ」
この決定に際して、レースを運営するDORNAは、アメリカ人ライダーのジョー・ロバーツが望ましい、と考えていたようだ。Trackhouse Racingはチームの母体がアメリカ系であり、そこにアメリカ人ライダーが参戦するのは無難な選択で、世界を視野に入れたマーケティング面でも八方丸く収まるように見える。だが、ブリビオはDORNAの願望を忖度するのではなく、あくまでもチームとしての意思でライダーを選択した、と述べる。その事情については、以下のように説明している。
「アメリカのチームにアメリカ人ライダーが理想的であることは、我々は今までにも公言してきた。だから、ジョー・ロバーツは我々の有力候補だった。彼を候補として検討していたし、スポーツ面でのポテンシャルについても自分たちなりに評価をした。(評価の結論が)正しかったのか間違っていたのかは、2年後にわかるだろう。とはいえ、先ほど言ったように我々は選択をしなければならない。だから、自分たちなりの評価と分析で、我々のプロジェクトには藍が相応しい、と判断した。パスポートの国籍に関わらず、ね」
小椋の何を評価したのか、という点については以下のとおり。
「どちらの選手を選んだところで、ともにMotoGPの経験はない。どの程度戦えるのか、というのは後になってみなければわからない。藍はMoto2ですでに何勝か挙げており、レースでも粘り強くしたたかな走りをする、と私は見ている。グリッド位置がよくなくて後方スタートでも、諦めずに順位を上げていく。MotoGPになれば、あのスタイルはさらに磨きがかかるだろうと我々は考えている。他にもいろいろと理由はあるが、彼を選んだのはいいチョイスだと思っている。とはいえ、それは今の段階での考えで、それがどうなるかは将来のことだ。我々としては自信があるし、いい選択をしたと思っている。まあ、見ていてほしい」
また、小椋のレースキャリアでここまでずっと行動を共にしてきたクルーチーフのノーマン・ランクは、来シーズンには帯同しないようだ。ブリビオによると、小椋はTrackhouseのクルーチーフと仕事をすることになる予定だという。
と、この質疑応答からも、小椋のステップアップはいわゆる「日本人枠」によって選ばれたものではないことが見て取れる。過去にこのような形で欧州メーカー(小椋の場合はあくまでサテライトチームだけれども)に抜擢された選手というと、誰しもすぐに思い浮かぶ名前は原田哲也だろう。1990年代、アプリリア250cc時代のファクトリーチームに三顧の礼を持って迎えられ、このチームから最高峰の500ccクラスへも参戦した。原田の後は、〈ニトロ〉芳賀紀行がSBKでの大活躍を評価されて、アプリリアファクトリーチームから2003年のMotoGPへ参戦している。この当時のアプリリアは、コスワース製の3気筒エンジンを搭載したRS3(cube)というマシンだったことをご記憶の方もいるだろう。
その後、アプリリアはMotoGPから一時的に撤退してSBKにすべてのリソースを集約するが、その時代に中野真矢もMotoGPからSBKにスイッチし、アプリリアファクトリーチームからRSV4で参戦している。
彼らのように、小椋が日本メーカーの後ろ盾を頼ることなくMotoGP参戦を実現させたのはじつにたくましいかぎりだが、日本企業の後ろ盾がないということは、契約や様々な身の回りの交渉ごとをすべて自分で解決しなければならない、ということでもある。ヨーロピアンライダーの場合、カルロ・ペルナートやパコ・サンチェスなど、パドックの機微を知り尽くした辣腕マネージャーたちが業務を一手に引き受けることが多い。契約社会といっても、そこに記された文言は一見不可侵のようで、じつはそれを扱う人とその場の状況でなんとでもなってしまうのはよく知られた話だ。理不尽な事態に泣く者や契約を盾に高笑いする者の具体的な例など、枚挙にいとまがない。
そこのところだけには、くれぐれも気をつけて、優秀なマネージメントスタッフを味方に引き入れてほしい、と願うものであります。
というわけで、またしてもやたらと長くなってしまったので今回はここまで。すみません。ではまた。
(●文:西村 章 ●写真:MotoGP.com)
web Sportivaやmotorsport.com日本版、さらにはSLICK、motomatters.comなど海外誌にもMotoGP関連記事を寄稿する他、書籍やDVD字幕などの訳も手掛けるジャーナリスト。「第17回 小学館ノンフィクション大賞優秀賞」「2011年ミズノスポーツライター賞」優秀賞受賞。書き下ろしノンフィクション「再起せよースズキMotoGPの一七五二日」と「MotoGP 最速ライダーの肖像」、レーサーズ ノンフィクション第3巻となるインタビュー集「MotoGPでメシを喰う」、そして最新刊「スポーツウォッシング なぜ<勇気と感動>は利用されるのか」(集英社)は絶賛発売中!
[MotoGPはいらんかね? 2024 第10戦イギリスGP|第11戦オーストリアGP|第12戦アラゴンGP]