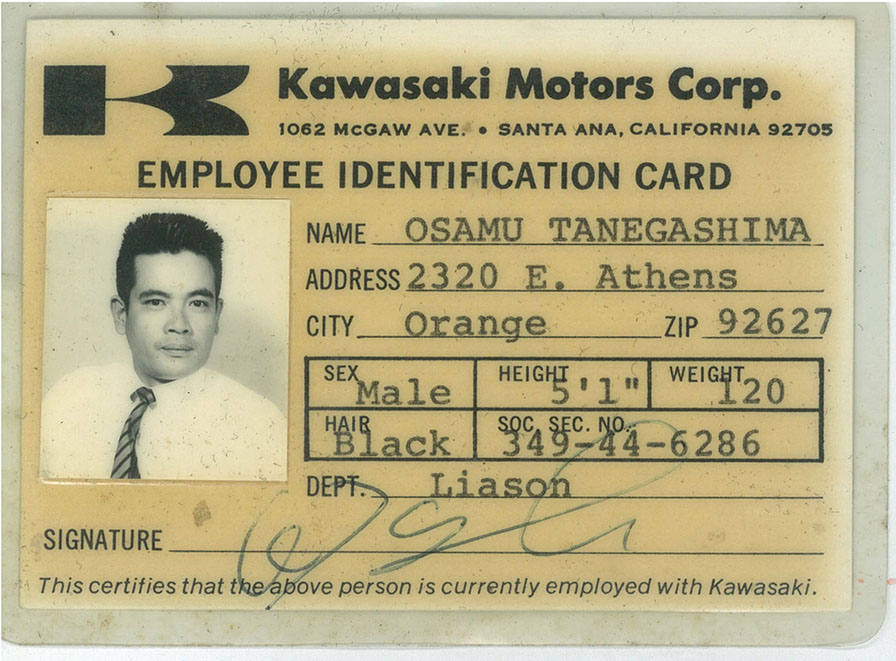第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた後の物語である。
※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。
カワサキのミスター・スミス
ボスは日本へ去り、私は再びホリデイ・モーテルに陣取って、商売開始の準備にかかった。シカゴを直撃した雪は、三月十日を過ぎても東部各地を荒れ狂い、各地に被害を生ぜしめていた。なにはともあれ、新築ビルに電気、ガス、水道、電話を引くべく駆け回ったが、いずこも雪害対策に追われており、いっこうに来てくれなかった。万事手っ取り早く、かつサービス精神に富む米国では、全く異例のことであった。
悪戦苦闘の末、まず電話会社が来た。工事責任者のフランクは、遅参をわび、私に非常な親しみを示し、かつ「コンニチワ」などと口走るので、昼食をともにしたところ、「GIで日本に二年いた。日本も日本人も大好きだ」という例の話である。簡単な打ち合わせの結果、電話は一日で通じるようになった。
机やキャビネット類は、B社の紹介で、ニューヨークから運び込まれてきた。電話と机が入ったので、私はホリデイ・モーテルから事務室に移ったが、暖房のないダダッ広い建物は寒く、セーターやオーバーを重ね着し、それでもたまらなくなると体操したり、倉庫を走ったりしていた。電気会社など、今にも来るようなことを言うので、こんなにしてでも、事務所に頑張らざるを得なかったのである。
電話会社のフランクは、ちょいちょい立ち寄っては馬鹿話をしていたが、とうとう見かねたのか、「サムよ、私に『カワサキのミスター・スミス』と名乗らす気はないかね」と言い出した。
「なんの冗談だい」
「この雪だ。電気、ガス、水道の各社がなかなか動けないのはわかるけれども、申し込んで十日経ってもまだ来ないというのはひどすぎる。私が、カワサキ代表としてプッシュしてみたいのだが」
「恩に着るぜ」
彼は、その場で各社に電話してくれた。同じ性格の事業に身を置いているだけに、交渉のツポをうまく押さえてくれたのだろう、雪もだんだん小降りになり、各社とも若干の余裕ができたこともあったろう、間もなくわれわれの建物には、これら文明の恵みが通じ、オーバーなしで仕事ができるようになった。
一夜、私はフランクをニューヨークの日本料理屋に招待した。彼は日本飯を本当に楽しんでくれ、「困ったことがあったら言えよ。力になるぜ」と繰り返し言った。
彼は、中学卒の学歴しかなく、電話会社では、社内講習と試験に耐え抜いて、フォアマンの地位を確保した苦労人であった。彼はまた、「サム、君はニューヨークで生まれたヤツみたいな運転をするな」と言い、私は、随分長い間、これをほめ言葉と取っていたのだが、実は「お前の運転は荒っぽすぎる」の意味であることが、後に判明した。
リンデン兵舎
電気などが通じて間もなく、日本からYとAの二名が着任した。
Yは工場からの出張者であるが、日米の部品供給システムを完成するため、かなり長期の滞在を予定していた。
Aは、私より遅れること一ヵ月でシカゴの部品会社に赴任、部品業務ほとんどを一人でやっていたが、今度部品会社の業務を実質的に当地に移すことになり、それに先立って着任したのであった。
モーテル暮らしは不経済だし、この辺で日本飯にありつくには自分で炊く以外にないことが判明したので、私たちはアパートを借りることにした。ところが、西部ではいくらでもあった家具付きアパートが、この辺ではなかなか見つからなかった。西部は人の動きが激しいが、東部では定着性が高いことによる。やっと見つけたリンデンのアパートも、三人が少なくとも三ヵ月いることを条件に、家具を付け足してくれた。
スキップたちが移動して来るのは四月になってからだが、それ以前の準備が、それぞれ結構あった。疲れ切ってアパートへ帰るのは、毎晩九時か十時。「料理職人」の腕をお持ちのお二人は、まず風呂などに入られる。ほかに芸のない私は、着替えもそこそこに、前日の汚れ腐った鍋、釜、フライパン、茶わんの類を洗わねばならぬ。無精者の私にとっては地獄の苦しみだが、これが最初からの約束だし、この工程を済まさぬことには飯にありつけぬ以上、仕方がなかった。
「おい、済んだぞ」の声に応じて、お二人は風呂場から出てくる。Yはステーキなどの西洋料理に本職はだしの腕を持ち、Aはうどん、まぜ飯、おでんなどの日本調を得意としていた。入れ違いに私は風呂に飛び込み、出てきたら最後、ビール、ウィスキーをガブガブやることと、出てくる物を次々に平らげるのみ。もう、テコでも動くことではなかった。
よその地域からの出張者は、「招待」と称して引っ張り込んだ。もし彼らに料理の才がない場合、私は容赦なく洗い仕事を押しつけ、そういった夜だけは、早々と酒飲みを始めて、極めて幸せなのであった。
この生活は、六月にAと私の家族が来るまで続き、工場の連中は、ここを「リンデン兵舎」と称したのであった。
スキップ一座
四月初旬のある日、スキップとその配下五名が、シカゴから着いた。スキップ以下、管理部門担当で私の昔馴染みであるバル、サービスマネジャーのダン、後述のいきさつで参加した部品担当のバート、それにスキップの秘書のイブ、モーターサイクル出荷担当のキャシーの女性二名も加わっていた。
スキップとイブはビュイックで飛ばし、新婚のバート夫妻はかなり古いサンダーバードで従い、バルとキャシーは、ダンが運転し書類一切をキャビネットごと積み込んだ大型トラックに便乗しての、大移動であった。
バルは家族をシカゴに残したままで、「月一回、家族と会うため、会社負担でシカゴに帰ること」を雇用条件の一つにしていた。かように家族と離れて暮らすというのは、彼のごとき健全な米国の家庭人にあってはすこぶる異常なことで、「これは奴さん、長くいる気はないのだな」と思った。
スキップは、何人目かの妻をロサンゼルスに残したきりで、それがイプのことを感づき、ゴタゴタしている様子だった。ダンは、これも数回目の離婚訴訟の最中であった。
一座は、会社の近くのモーテル、ハワード・ジョンソンに二〜三泊した後、バート夫妻を除いた全員が、家具付きアパートに引っ越して行った。スキップとイブが一室、バル、ダン、キャシーがそれぞれ各一室を占めていた。これも米国人としては実に奇怪なことに、彼らはアパートに電話を引かなかった。「ここは休息の場だ。電話でわずらわされたくない」というのがスキップの言い分であったが、実際にはロサンゼルスの若妻に、三時間の時差を利用されてギャアギャアやられるのがたまらなかったのであろう。ただ、かような点についてまで、スキップが電話なしなら、バルもダンもこれにならうというあたり、このグループの性格を現わしているようであった。
かように、問題点を挙げ出せばキリのない連中ではあったが、ただ彼らの仕事にかける情熱と頑張りについては(そのやり方や効率性はともかく)、誰も文句のつけようがなかった。始業は八時三十分であったが、彼らは八時には勢揃い。「飯だけは落ち着いて食わしてくれ」というバル以外は昼食も事務所で、仕事をしながらサンドイッチ類をほおばり、夜もわれわれリンデン兵舎の面々と同じく、毎晩九時過ぎまで仕事をした。
スキップは、電話で各セールスマンに「カワサキの会社になるんだ。五月からはサムライも売れる。頑張れよ」と檄を飛ばしていた。
彼のセールスマン・コントロールは一貫して電話であり、事務所に呼びつけるのはクビにする時くらい、自分が現地に出て行くことは一切なかった。私は、販売方針に関して打ち合わせしようといろいろ準備していたのだが、彼はいっこうに乗って来なかった。彼自身は販売の職人で、方針的なことにはあまり興味がないのと、「グズグズ言わずにまかしてくれ」という感情の、両方が原因だったのであろう。当方が示す案にはほとんど文句をつけず、一、二の機種の末端価格にケチをつけた程度で、西部開店の際、アランと火の出るような議論を闘わせながら一つ一つの方針を決めていった私としては、拍子抜けもいいとこであった。
バルは、新しい帳票制度の作成に余念がなかった。見ていると、シカゴ時代の敷き写しなので、「今度の販売量はケタが違うぞ。会計機や小型コンピュータの導入まで考えとかないと、帳面が販売に追いつかなくなるぜ」と忠告したが、「これはオレの仕事だ。心配するな」の一点張りだった。これは、実は彼自身、会計機やコンピュータには全然知識のなかったことによることがだんだんわかっていくのだが……。
ダンは、倉庫の片隅に、自分で修理工場を作っていた。季節性のこともあって東部の経費は徹底的に締めるのがボスの方針であり、特に修理工場は、レース気違いのスキップやダンが控えていることもあって、気の毒なほどわずかな予算しかつけなかったのだが、それでもダン氏、一生懸命トンカチやっていた。
バートは、Aの指示の下、少年たちを使って、部品倉庫を作っていった。
イブは、秘書として卓越しているのみならず、ヤマハでの永い経験からこのビジネスのどの分野にも通じており、機に応じて、積極的に電話交換手になったり、出荷を助けたり、帳面を手伝ったりした。彼女のかような働きぶりと、控え目で明るい性格がなかったならば、スキップと彼女との公私にわたる関係は、会社組織をゴチャゴチャにしたことであろう。
キャシーは、モーターサイクル出荷部門の責任者として、一人ずつ地元の女子を採用しては、それを訓練し、少しずつ出荷部門の組織を作り上げていった。そのやり方はまことに見事で、お茶くみと雑務のみに終始する日本企業の女子事務員との違いに、思いを馳せたものである。
かくてリンデン兵舎勢とスキップ一座に、少しずつ土地の人間を加えながら、五月一日の販売開始に向かって、一心不乱の準備が続いた。
「表組織」と「裏組織」
シカゴの東部代理店時代、販売担当副社長のスキップは、事実上モーターサイクル関係のすべてを握っており、管理部門担当のバルもその配下であった。
しかし、スキップは基本的にセールスマンで、経営はその任ではなかった。したがって管理的なことで頭を使わすのは得策でないし、また販売と管理とは本来、チェック・アンド・バランスの関係にあるべきなので、新会社発足に当たり、「スキップは販売の長、バルは管理の長、両者は平等であって、サムが双方をみる」とボスが明言、両者も表面上は納得していた。これが「表の組織」で、サービスはスキップに、出荷はバルに属した。
だが、「裏の組織」ではスキップ座長がいぜん、バルも含めた全体の親方で、バルは、私の指示も、ほとんどの場合スキップに確認してからでないと実施しなかった。それとなくさぐってみると、どうもスキップは、「日本人と話をするのは非常にむずかしい。彼らが本当になにを考えているかを理解し、彼らにこちらの考えを本当に理解させるのは、オレのように、ヤマハで永年苦労してきた男にしか無理だ。お前たちが、直接サムと話をして、なにかわかったような気になると、えらい目に遭うぞ」とふれ込んでいるらしかった。
かようなややこしさは、当然予想されたところで、ボスは次のように言っていた。
「サムよ、今度は精神衛生上よろしくなかろうて。シーズンを逃がすわけにはどうしてもいかんから、東部代理店とも妥協せざるを得ないし、その最たるものが、スキップ以下従業員と販売店の引き継ぎだ。今シーズン売りつないで、B社在庫の旧型車も売り、東部代理店の売掛金も回収するには、スキップでいかざるを得んがね」
部品業務は、リンデン兵舎のAが直接握っていた。彼は、シカゴの部品会社時代、新合弁会社が設立された際の自分のアシスタントとして、当時東部代理店のサービスマネジャーであったバートに目をつけた。スキップは、「バートは馬鹿なので、近くクビにする。君のアシスタントには、米国一のパーツマネジャーをつれて来てやる」と言ったが、Aは、「私はバートを使いたいんだ。サービスマネジャーとしてクビになっても、彼がニュージャージーに移動するよう手配されたい」と頑張った。
このため、バートは、サービスマネジャーの職はダンに奪われ、シカゴからの移動でも、彼ら夫妻だけは、自分たちの古いサンダーバードでやって来たのだった。当地でも、スキップ一座のアパートには入れてもらえないため、彼ら夫妻はリンデン兵舎アパートに一ヵ月おり、やがて、もっと安いアパートへ移って行った。
なんやかやとゴッタ返してる最中、オーナーの一つたるB商社の東京から、Sという社員がやって来た。
「オレの机はどこだい」
「どこにもなし」
「冗談じゃないですよ。三五%出資してるんだからね、ウチは」
私は彼を外に連れ出し、ヘルメットを渡し、サンプル車として置いている二五○CCA1を示した。
「乗んな」
「オレはカブしか乗ったことがないんだ。いやだよ、こんな大きなヤツ」
「じゃあ帰んな。その一言で、お前さんはここにいる資格なしだ。ホンダのスーパーカブしか乗ったことがなく、ウチが必死で売り込んでる看板商品のA1サムライを『いやだよ、こんな大きなヤツ』とは、一体何事だい。お前さんたち商社マンは、鉄だろうが缶詰だろうが衛生サックだろうが、手当たり次第に売んなさる。だがな、オレたちモーターサイクル屋は、モーターサイクルが好きだから、モーターサイクルをやってるんだ。ここの連中もみんなそうなんだ。本気でモーターサイクルやりたいんなら、商社なんかやめて、販売店でのデッチ奉公から始めるんだな」
事前工作もやったし、若干の後日談もあったが、B社からの出向は、終始一貫認めなかった。機能のハッキリしない日本人がウロウロすることは、われわれの組織にあっては百害あるのみだし、そんなヤツに給料を払う余裕もなかった。
かくして新会社は、相変わらず日米間の往復を続けているボスを長とし、私が直接責任者として現地に坐り、スキップとバルを両輪として、「スキップ一座」の裏組織を内包しながら、開店の日を迎えたのである。
開店の日々
前年四月、シカゴでの部品会社開店披露は、コンティネンタルプラザとかいう一流ホテルでやり、客の九○%は日本人だった。
前年十一月、ロサンゼルスでの販売会社開店披露も、ヒルトン・ホテルでやり、客の過半数は日本人であった。
だが、今回の「イースタンカワサキモーターサイクル」のそれは、事務所のすぐ近くのハワードジョンソン・モーテルで、販売店を主体に行なった。客の九○%以上は米国人で、ニューヨークからわざわざ駆けつけて下さった日本企業の方々は、手持ち無沙汰気に仲間うちで暫く話された後、早々に引き上げて行かれた。「米国人」といっても、販売店主体とあって、皮ジャンパー、Tシャツ、ジーンズという面々が多く、誇り高き日本企業の方々の話し相手になる手合いではなかったのである。
ちなみにこれより二年後、このイースタンカワサキとガーデナのアメリカンカワサキとが合併、全米をカバーする販売会社を設立した時のパーティは、サンタアナの同社屋でやった。われわれの現地化が進むにつれてパーティが簡略化され、業務上関係のない日本人の出入りが減って米国人の比率が高まるのは、興味深いことであった。
それはともかく販売店は、二五○CC A1、三五〇CC A7、六五〇CC W1などのニューモデルに、飢えかわいていた。モーターサイクル雑誌の記事やマニア同士のうわさ話は、これらが画期的な性能のクルマであることを騒いでいるのに、B社への支払いのゴタゴタで東部代理店はこれらを仕入れすることができず、したがって彼ら傘下販売店も、みすみす商機を逸し続けていたのである。
注文の電話が鳴り続いた。スキップは、これらニューモデルと抱き合わせてB社所有の旧在庫を売り、併せて東部代理店の売掛金を回収しようと努めた。「こんなややこしい営業は初めてだ」と彼はぼやいたが、これら三種類のものをつけ分けているわれわれの帳簿も、世界に類のないややこしさだった。
出荷は注文に、帳面つけは出荷に、常に間に合わず、やがてニューモデルの在庫が底をついた。私は、次の船が着くまでのつなぎに、西部のアメリカンカワサキの在庫を買って陸送したが、B社はこの分についてまでコミッションを要求し、私を激怒させたりした。
シーズン最中に新しい会社を興して販売を開始するというのは、米国人が大好きなフロンテア、チャレンジングなどの感じにビックリだったのであろう。異様な熱気が、地元採用のおばさんたちまで支配し、夜七時過ぎに夫が子供を連れて迎えに来たのを、血相変えてどなりつけ、追い返すような光景も見られた。
暗雲の発生
六月に入っても、売れ行き好調は続いた。ホンダ、ヤマハが、前年に続いて販売不振に苦しんでるのを知っている私は、「両社にくらべて販売劣弱なウチだけが、いつまでも好調でありうるはずがない」と考え、「さて屈折点は七月か八月か」と頭をひねっていた。運用しうる資金はごく限られており、「仕入れは慎重にやれよ」が、ボスの至上命令であった。
七月に入ると販売が激減した。対前月で落ちているのみならず、七月の販売計画に対しても大きく落ち込むことが明らかになった。
ボスから電話がかかってきた。
「七月第二週までのレポートを見た。いよいよ来よったな、これは」
「そのようですな、やっぱり」
「しょせん、二ヵ月間支えるだけの販売力しかないわけか……。さて、仕入れを締めるか」
「八月中旬神戸港発の五百台をキャンセルしたいんですが」
「そうして様子を見よう。もし持ち直したら、西からまわしてもいい。ともかく今、東部で在庫を抱えたら、どうにもならんぜ」
八月に入ってまた落ちた。われわれが引き継いだ販売店は、都市部にあってはホンダ、ヤマハを主力に売る店、田舎にあっては部品もロクに持たぬ零細店が多く、カワサキを売る熱意と技術の双方に問題があった。したがって、クルマの人気ともの珍しさで売れる間は売るが、それが過ぎると、もう支えようがなかったのである。
私は、予算の抜本的な見直しを行ない、経費を徹底的に引き締めて、冬ごもり態勢に入った。(続く)