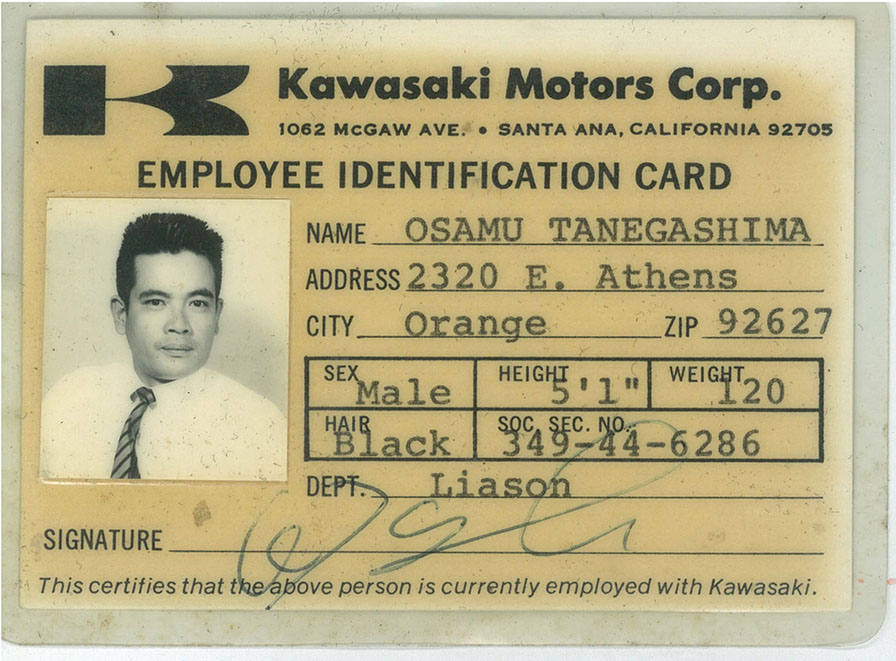第二次世界大戦に敗戦後、1950年代半ばから急速な経済成長を遂げた日本。1960年代になると力を付けた国内二輪メーカーは世界市場、特に巨大なマーケットである北米への輸出を本格化すべく試行を重ねた。今日では押しも押されぬ大排気量メーカーのカワサキだが、北米において初めてシカゴに駐在事務所を開設したのは1965年7月。この年の10月、待望の大排気量車W1が完成、いよいよ北米輸出に本腰を入れ始めた。これは、そんなカワサキの海外展開黎明期に単身渡米したサムライ、種子島 経氏の若き4年間の日の奮闘の物語である。この経験が、後にマッハやZの誕生に大きく関わるのだが、それはまた別の物語である。
※本連載は『モーターサイクルサム アメリカを行く』(種子島 経著 ダイヤモンド・タイムス社刊・1976年6月25日発行)を原文転載しています。今日では不適切とされる語句や表現がありますが、作品が書かれた時代背景を考慮し、オリジナリティを尊重してそのまま掲載します。
フレズノ=ふざけた販売店志願者
次の訪問地のフレズノからは、出発前にシカゴの部品会社あてに「カワサキ販売店を開きたい」旨の手紙が寄せられていた。新しくカワサキ専門の店を開くというのは、当方としてみれば最も歓迎すべきお客というわけで、モーテルに着くとすぐ電話をかけ、翌朝の訪問を約した。
翌日訪ね当てたのは町外れの小さな家。主人公は二十歳前後の青年であった。
「私の妻だ」と紹介されたのは、高校生みたいな感じの少女で、そのくせ、この国の習慣通り、コーラびん片手にダンナと一緒に坐りこむ。
「大学に行ってるんだが、いい加減飽きたしね……。バイクが好きなんだ。ホンダの三〇五CCを持ってる。フレズノにはカワサキの店がないから、どうせなら新らしいもの、と思ってね」
「金? 私たち夫婦は一文なしだ。父が少しは出してくれるだろうし、友人からも少々集まるだろう。一体、どのぐらい準備したらいいんだい?」
私はトムとの話を踏まえて、「これだけの町で、一軒だけのカワサキ専門店をやるのなら、最低三万ドル、できれば五万ドルほしいな」と言った。
「三万ドル? 冗談いうなよ。三千ドルならなんとかなるかもしれんがね」
私は、「バイクに乗るのは楽しいが、モーターサイクル・ビジネスはもっとまじめに考えないと駄目だぜ」と、訓戒を残して去った。
こういう了見で「バイク」を始めた手合いが、一九六六年現在どんどん破産しているのであり、こちらこそ「三千ドルかそこらでフレズノのフランチャイズを買い取ろうとは、冗談いうなよ」である。
このフレズノからは、私がガーデナに帰ってから、ヤマハ販売店がアパートに電話してきた。この男は、業界のうわさでは「アル中で相当ボケとる」ということなので放っておいたら、今度は「ウィルソンのトライアンフ」として一九二九年以来の老舗を誇るダグ・ウィルソン二世が、「日本車をやらねば損だ」とばかり乗り出してきた。
われわれの開店後、ベーカースフィールドのトムとこのフレズノのダグとは、適当に協力しながらこの一帯をガッチリ押さえて、現在に至っている。
文句だけは一人前の販売店
フレズノを後に、一日二〜三軒ずつ販売店を訪問しながら北上した。
わが西部代理店の不思議さは、フレズノやサンフランシスコのような大きな町に販売店皆無、サンディエゴ、サクラメントに各一軒しかないのに、この辺の小町村はそのすべてに、義理堅く一軒ずつ販売店を持っている点にある。リスト上の店をすべて訪問するということで出かけて来た私としては、一々つき合わざるを得ない。
これらの店は、ディーンと見た東部の販売店と同じくホンダ、ヤマハで食ってるのであり、カワサキは「置いてやってる」に過ぎない。カワサキへの愛情も親しみもないため、当方への態度は剣もホロロ、面接の相手をつかまえて坐らせるのが一苦労だった。
やっと話し相手になってくれても、言うことは文句ばかりである。
「手持ちのマシンを売り払ったら、もうカワサキはやめだ。詐欺にかかったようなもんだよ、実際。最初のふれ込みは結構だったが、西部代理店のサービスがなっとらん。こんなことでは、お客に迷惑かけて、ウチのノレンにキズがつくのが落ちだ」
「日本のモーターサイクルはどれもこれも同じだ。ホンダ、ヤマハ、スズキでもう沢山だよ。工場直販で出て来るのは勝手だが、買う人はいまいて」
「カワサキも直販やるんだろう。苦しい間は米国人にやらしとって、もうかるとなれば乗っ取る。これが日本人さね」
文句だけはひとくさり言うが、当方の具体的な質問に対しては、「忙しい、時間がない」と逃げを打つ。これで当方の言葉が自由にまわるならば、当然ケンカになるべき場合がいく度もあった。
市場規模のせいもあって、ほとんどが日本のサブ店並みの大きさ。少人数でバタバタやっており、西部代理店を責める割りには、彼ら自身のアフターサービス体制も頼りなかった。
たまにあるちゃんとしたモーターサイクルショップは、ホンダ、ヤマハ、スズキ、トライアンフ、BMWと、あらゆる銘柄を揃えて近隣一帯を押さえており、カワサキなどという素性も知れず商品特性もないクルマをまじめにやる気は、さらさらなかった。
夜、モーテルに着いては、一店ごとのレポートをタイプアップした。カワサキが直販を開始する場合には、このドサ回りレポートが、販売陣の基礎資料になるのだから、キッチリ整理しておかねばならなかった。
各店を<A=是非ウチの販売店にすべし>から、<E=販売店にすべからず>までの五段階評価したが、ベーカースフィールドの<A>を除いては、<D>と<E>のみふえた。
ユーリカ=金曜の夜
レッディングから分岐する二九九号線は、すさまじい山道であった。アップ、ダウン、急カーブの連続。「時速五マイル以下」の難所もあり、シカゴやロサンゼルス周辺の高速道路だけで運転経験を重ねてきた私には、まことにもって難行苦行の四時間で、「モーターサイクルで来ればよかった!」と嘆く場面が何度もあった。
これだけの難行苦行の目的地は、カリフォルニア州の北端、太平洋岸のユーリカという一寒村である。
販売店リストを地図上にプロットした時、このユーリカだけが一点とび離れており、これを省略すれば二日の節約になるので、そのことを考えないでもなかった。しかし、「ユーリカモーターサイクル」は毎月コンスタントな販売を挙げているようなので一度見ておきたかったことと、例の「リスト上の店をすべてつぶす」という方針から、かくは出向いて来たのである。
ユーリカは漁村であった。いつもの通り、町に入ってすぐ見えたガソリンスタンドで所番地を示し、訪ね当てた「ユーリカモーターサイクル」は、カワサキの看板は出していたが、閉まっていた。
金曜日の午後四時過ぎというモーターサイクル屋の書き入れ時に奇怪なことである。モーテルでレッディングの店のレポートをまとめた後、念のため六時半頃電話してみると、「会いたい。すぐ来てくれ」という返事である。
早速昼間さがし当てておいた店に行くと、今度は中に入れた。見ると、新車はカワサキの三台だけ。ほかに下取りの中古車が数台置いてある。部品在庫はほとんどなく、修理工場には簡単な工具類が転がっていた。
「従業員はいない。私だけだ。ウン、私は郵便局に勤めていて、月曜から金曜の午後五時半以降と、土曜日だけやってる」
「開店したのは二年前だが、西部代理店からは誰も来たことがないし、日本人を見るのは君が初めてだ」
「年に新車が三十台は売れるから、いい小遣い銭稼ぎになる。ユーリカは小さな町だから、ここでカワサキのように人の知らない銘柄でフルタイム販売店をやるのはむずかしい。ホンダ、ヤマハは、もちろんフルタイムだが、今年は赤字だって話だ」
夏の金曜日の夜とあって、結構客がついているので、晩飯の誘いは断わり、モーテルでこのパートタイム販売店に関するレポートを叩いた。
さて、なにはともあれ、今日は金曜日である。この五日間に、十分間で追っ払われた所も含めて、十五店回ったわけだ。少しはましな晩飯でも食うかというわけで、町中をブラブラドライブし、魚料理の看板を掲げた店に入った。
馬鹿のひとつ覚えのスコッチ水割りを二〜三杯やった。運転の緊張と運動不足のせいであろう、すっかり食欲が衰えているのを、ウィスキーでだますような感じで、珍しくスープから本格的に始めた。
九時過ぎ頃から、席は次第に詰まってくる。男―女、男―女のペアばかり。狭い町のこととて、みんな顔見知り同士のようで、出会い頭に抱き合ったり肩をたたき合ったりしている。若者用の場所はほかにあるのか、ここは中年以上のペアばかりである。
やがて楽隊が入って、フロアではダンスが始まった。踊る人々。それを取り巻く応援団のような人々……。
さらにその外でテーブルについている人々。踊り手同士、応援団やテーブル組との間でにぎやかな掛け声がとびかい、小さな料理屋全体が、週末の夜の楽しい雰囲気を盛り上げていった。
その中で、私だけはポツンと水に浮かんだ一滴の油のよう。土台、一人で坐って飯を食ってるというのは私だけで、これだけでも異様なのである。考えてみるまでもなく、朝も昼も晩も、ほとんど一人きりで食っていたわけだが、いつもはほかのことに夢中で気にもとめなかったのが、このユーリカのエアポケットの夜、忽然と人間臭い思いにとらわれたのである。
私は妻と二人の子供を差し当たり妻の実家に疎開させている。妻の手紙と、四歳の娘の作文と、一歳の息子のわけのわからん絵とが三位一体となった封書がよく来たが、当方からの返事はあんまり出していなかった。
なんとか米国の地にカワサキモーターサイクルの根を下ろし、大体間違いなく給料の出るメドをつけて、一家を構えたいものだ。しかしなあ、こういうガラクタ販売店やパートタイマーではなあ……。
ひょうきんなばあさんが、私をダンスに引っ張り出してくれた。いい加減に手拍子、足拍子をとって一区切りつくと、マティニをおごってくれた。こちらでもおごり返し、ワアワアやっているうちに、「GIで日本に三年いた。いい所だ。トーキョー、タチカワ、オジョーサン……」という例の手合いまで出現。山道ドライブの疲れもあってか、ベロベロに酔っ払った一夜であった。
サンフランシスコ=パートタイマー店主
カリフォルニア州第二の都市たるサンフランシスコに一軒の販売店もないことは、確認済みであった。だが、ユーリカからゆっくりドライブして来て、どうやら日も暮れたし、土曜日でもあるし、ま、今夜はここで寝るかというわけで、金門橋から町のどまん中に突っ込んだ。
モーテルでシャワーを浴びてから、車で坂道だらけの市内を一回り、チャイナタウンで晩飯を食った。
モーテルに車を駐車してから、今度は徒歩でそれらしいバーを二〜三軒歩き女あさりを試みたが、いっこうに収穫もなさそうなので、早々と寝てしまった。
さて、翌日曜日の朝、「休んでるかな」と思いながら隣町のサウスサンフランシスコの販売店に電話すると、意外にも四〜五歳とおぼしき女の子が出てきた。「開店しているのなら、午前十時頃訪問したい」と述べたてるのに対して、いかにも子供らしいはっきりした物言いで、「アイ・キャン・ノット・アンダスタンド・ユア・ランゲージ」ときた。この辺が、私の英語に対する正当な評価だったのであろう。とはいえここで引っ込んでは商売にならないので、ねばってなんとか主人公を引っ張り出し、訪問の約束を取りつけた。
訪ねて行った店は、当時の日本の自転車屋並みのスペースに、中古車とヘルメット、変型ハンドル、シートなどのアクセサリーがゴタゴタ置いてある。新車は一台もなく、純正部品の保管庫もない。
主人公は、これも中年のパートタイマー。近くの工場の機械工だが、エンジン物をいじるのが大好きなので、小遣い銭稼ぎと趣味を兼ねてやっており、新車のフランチャイズはカワサキだけという。ここでも、「カワサキはクルマも部品もいっこうによこさんが、一体どうなってるんだい」と、文句だけは一通り聞かされた。
奥さんが帳面つけを担当しており、「アイ・キャン・ノット……」のおじょうさんは、店の中を走り回って遊んでいる。
米国の販売店では極めて珍しいことに、店のすぐ裏が自宅である。「サウスサンフランシスコの販売店がパートタイマーではまずいかい。条件が整えば、フルタイムになる気はあるんだぜ」と、さかんに気にしていた。
「昼飯を一緒に食おう」というのは断わった。だが、「娘が悪いこと言って済まなかった。きつく叱っておいた」と言い、おじょうさんを呼んで「アイ・アム・ソーリー」を言わせたのには、「気にしていない。子供は正直であるべきだし、あれでいいんだ」と、精一杯かばってやった。私の娘と同じ年頃のその子はなかなか可愛かったし、そんなことでお尻を叩かれては可哀そうだったからである。
だが、ビジネス上の結論は、はっきりしていた。私ははっきり言った。
「われわれがやる以上、それはフルタイムのビジネスであり、販売店にもフルタイムでカワサキをやってもらわねばならぬ。サウスサンフランシスコのような大市場にパートタイム販売店など、とんでもない」
暗い疑問
フリーウェイ一〇一番は、カリフォルニア州の別名をとって「ゴールデン・ステート・フリーウェイ」とも称する。太平洋についたり離れたり、山から出たり入ったり、サンフランシスコ〜ロサンゼルス四百マイル(六百四十キロ)を、まことに快適なドライビングで結ぶ。
この沿線にはリストアップされている販売店は二つしかないため、途中一泊しただけで、月曜日の夕刻、ガーデナのアパートにたどりついた。
この八日間の日課をならすならば、販売店とのインタビューが四時間、レポート作りに三時間、ドライブが五時間、というところだった。最後の三日間は、疲労のためにほとんど食欲がなく、窓を開け、左手を窓に乗せて運転したため、左手だけが猛烈に日焼けして、皮がマダラにはげていた(たとえレンタカーでも、エアコンディション付きには手を出せないような、日本的な遠慮があったのだ)。
しかも、これだけ苦労した結果得たものは、「もし、こんな販売店網しか得られないのならば、日本と同じく米国でも、後発は伸びられないのではないか? 新しく食い込む余地はないのでは?」という暗い疑問だけであった。
もしも、この段階まででレポートをまとめたならば、私の結論は、「カリフォルニア州で直販のメドなし。代理店を切り替えて、細々やらすべし」であっただろう。
シャワーを浴びている最中に、電話が鳴り響いた。西部代理店主からであった。
「帰って来たな。君がどことどこを回ってきたか、すっかりお見通しなんだ。はっきりしておきたいのだが、君が勝手に私の販売店を回って、いろいろなことを言うのは困る。わけのわからんヤツに時間をつぶされて、彼らも怒っている。今後私の販売店に出入りするのは一切お断わりだ。もしやるなら、訴訟だぞ」
「変なこと言うなよ。私は、君の販売店を回ってるんじゃなくて、カリフォルニアのモーターサイクル販売店を歴訪してるんだぜ。そりゃあ、なかにはカワサキを置いている店もあるけど、そこだけ避けたらかえっておかしいんじゃあないのかい」
半分屁理屈だが、この際止むを得なかった。
「ともかく私の販売店に出入りするには、相当の覚悟を固めることだな。
次に部品——。何回注文しても、日本からもシカゴからも来ないので、私は販売店に訴訟されかかっている」
「よろしい。緊急部品のリストを届けなさい。シカゴにあるものはすぐ出荷しよう。ただしCOD(代金引換払い)だよ」
「CODとは何事だ」
「君の店とは直接の取引関係はない」
「止むを得ん。それから六五○CC W1を十台、すぐまわしたまえ」
「クルマは一切駄目」
「フフン、訴訟で吠え面かくなよ」
彼は、日本人が概して訴訟に弱く、「訴えるぞ」と言えばおりやすい習性を利用すべくさかんにおどしているようだったが、私は取り合わなかった。