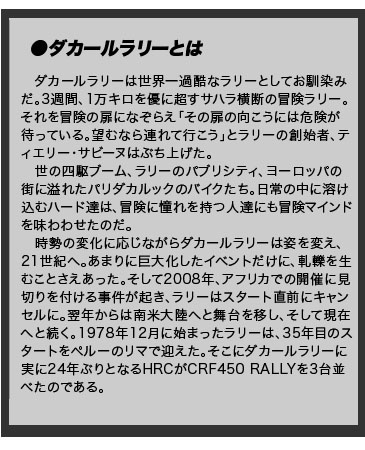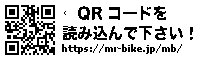Hondaは2012年を“オフロードの年”と位置づけ、様々な仕掛けをしてきた。まず全日本モトクロスではチャンピオン・成田亮を獲得し、チームHRCが大暴れしたモトクロスシーン、そして春にはCRF250Lをリリース。XR250以来途絶えていた250クラスフルサイズのHonda・デュアルパーパスの系譜に再び火を点けた。
そうした動きの中で7月に発表された“Honda、ダカールラリーに24年ぶりとなるワークスチームを送り込み復帰”というニュース。
松井 勉(以下松井):ダカールラリーへの復帰。これはいつ頃からの構想だったのでしょうか。
こちらで動画が見られない方、もっと大きな映像で楽しみたい方は、YOUTUBEのサイト で直接ご覧ください。
キャンプ地でダカールラリーの展開と今後に思いを馳せるTEAM HRCの代表、山崎勝実さん。長い夜はまだ始まったばかりだ。
11カ国30名以上のチームを束ね、全体を俯瞰する立場だった。
松井:各地域とは何を協議したのですか?
松井:そのビジョン、とは?
CRF450RALLYを短期間で実戦マシンへと育て上げた2012年。しかし2013年に迎えた初戦のダカールではあらためてその厳しさに触れる。ノーズ下に貼られたお守りが印象的。
松井:今、Hondaではこの先何年ぐらいダカールを続ける、となっているのでしょう?
松井:HRCの社長であり、二輪R&Dセンターのセンター長でもある鈴木哲夫さんは、ダカールのスタート、フィニッシュ地点に本社の上層部とともに赴き、ダカールラリーのスケールを目の当たりにされた、と聞きました。ラリーのコース脇に並ぶ人がまるで“箱根駅伝”のように途切れることがなく、チームスタッフが移動するサポート用の一般道でも、ダカールラリーの一行を一目見ようと、同じように観客が詰めかけていたと。
ライダーがステージでレースをしている間、チームスタッフもクルマ、飛行機で移動をする。山崎さんたちはホンダ・リッジラインに乗り連日数百キロの道のりを移動。サポートカーにも主催者から支給されたGPSが備わり、違法運転などがないか衛星を使って常に監視されている。
松井:2012年の準備から2013年の実戦を通じて、初年度の結果への評価としては?
松井:ある意味チーム作りの年でもあった……?
松井:そうした混成チームとして頂点を目指していくのか、それとも今後、もっとMotoGPのような優勝請負人達だけのエリートチームのようなカタチになっていくのか。どうするのでしょうか?
ダカールラリーとの関わりをより深める方針だというホンダ。ワークスチームの活躍もさることながら、プライベートで参戦するホンダライダーに写真のような“ホンダビレッジ”がダカールラリーのキャンプに現れる日も遠くないかもしれない。
松井:参戦するビジョンが理解できてきました。
松井:ラリー用市販バイクを出しているKTMは一つのビジネスモデルであると。
山崎勝実さんが語るダカールへのビジョンは明快だった。この世界一のモータースポーツに関わり、真正面から取り組み、戦い、時に破れ、強くも人間臭いダカールラリーに欠かせない挑戦者としてHondaが存在し続けること。そしてダカールラリーに挑むというプライベーターの後ろ盾になろうというのである。
次回はダカールへと続く開発の道、現地での苦悩、苦闘を体験したチームHRCの開発者達の声を紹介したい。(チームメンバー達のダカール編-に続く)
TEAM HRCのライダー、エルダー・ロドリゲス(ポルトガル・写真上)、ジョニー・キャンベル(アメリカ・写真中)、ハビエル・ピゾリト(アルゼンチン・写真下)が2013年ダカールに参戦。サム・サンダーランド(イギリス)、フェリッペ・ゾナル(ブラジル)の2名を含めた5名体勢で臨む計画だった。サンダーランド、ゾナルの2名はダカール直前の最終テストで負傷し、出場を断念する。
山崎勝実さんと(左)と、本田技術研究所 二輪R&Dセンターのセンター長兼HRC社長の鈴木哲夫さん。
Hondaはダカールラリーに戻ってきた。24年のブランクは大きいが、この先、ダカールラリーの一部となって歴史に名を刻むことになるのは間違いなさそうだ。