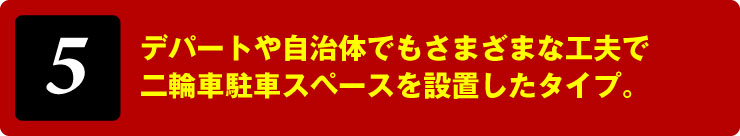
店リニューアル時に新設された東京・銀座三越の地下駐車場。

店舗のリニューアルに際して二輪車駐車場を設置したのが東京・銀座三越だ。
銀座三越といえば銀座四丁目の角にあり、戦前から銀座の顔の一つとして親しまれてきた存在。
昨年9月には売り場面積を1.5倍に増設。売り場、レストラン、屋上施設などを一新してリニューアルオープンし、話題となった。
そのリニューアルに際して新設されたのが、地下駐車場の二輪車スペース。
24時間営業で22台分のスペースがあり、利用料金は30分150円だが、同店で買い物をすると、その金額に応じて1〜4時間まで無料となる。
同店担当者は、「以前からお客様よりバイクの駐車スペースを設けてほしいという要望がありました。今回のリニューアル計画に際して、銀座地区にバイクの駐車場が極めて少ないこともあって、公共的な貢献の一つとしても設置することにしました」と話している。
デパートなど都市中心部にある商業施設で、こうした顧客サービスが広がれば、二輪車の駐車場事情は大きく改善する可能性がある。
そんな期待を抱かせる好事例といえる。つまりは、それがお互いの”益”につながるのだから。
自転車と自動二輪車が同居、東京台東区・入谷駅南自転車等駐車場。

自転車と自動二輪車が共用できるように整備された駐車スペースが東京都台東区にある。
東京都台東区の地下鉄日比谷線入谷駅の駅前に昨年7月にオープンしたのが、「入谷駅南自転車等駐車場」。
昭和通りと言問通りという幹線道路の交差点近くで、道路と道路に挟まれた三角州状の未利用地があり、そこに自転車と自動二輪車を駐車するスペースとして設置されたものだ。
自動二輪車は22台が駐車可能で、利用料金は30分50円、24時間最大で500円となっている。
台東区の担当者、都市づくり部道路交通課の片平 聡さんは、「現状からいうと、駅前などの駐車対策というと、自転車もぜんぜん足りていない状況で、今回も自転車駐車場の一部を自動二輪車用として整備しました。
今後も自転車を中心とする対策をとるなかで、その一部を二輪車用として、徐々に増やしていければと考えています」と話している。
歩行者用道路に設置された東京・大井町駅西口自転車等駐車場。

緑道沿いの歩行者用道路に二輪車駐車場を設置したのが東京都品川区の例だ。
東京都品川区のJR大井町駅西口のすぐ近くには、原付・自動二輪車専用の「大井町駅西口自転車等駐車場」が設置されている。
60台が駐車可能で、料金は24時間まで250円。200mほどの緑道となっている場所で、緑豊かな植え込みの片側が自動車も通れる道路で、反対側が歩行者用道路となっていた。
その歩行者用道路の部分に駐車設備を設置して、2007年12月に二輪車用駐車場としてオープンしたものだ。
品川区都市環境部土木管理課の担当者は、「品川区は、1981年に自転車対策の条例を定めましたが、その際、放置されているのは自転車、原付ばかりでなく自動二輪車も多いということで、自動二輪車も含めた規定を作りました。現在、品川区の自転車等駐車場で原付のとめられる場所は、ほとんど自動二輪車も含めてとめられるようになっています。この大井町西口の駐車場も、歩行者用道路に原付や自動二輪車の放置車両が多かったことから、むしろ駐車場として管理したほうがよいと判断して設置したものです」と話す。
この二輪車駐車場は、駅前にあることから人気が高く、ウイークデーで晴れた日はほぼ満車の状態となっている。
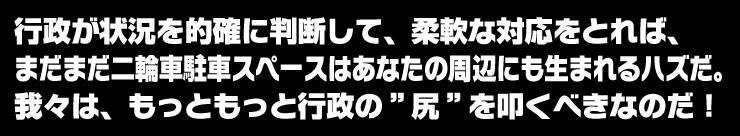
その状況の進展にリンクして、求められるのは二輪車の駐車スペースが「どこにあるのか」という検索システム。
各都市単位ではかなり充実してきているサイトもあるが、全国を網羅したものはないし、それが早急に求められているのも事実だ。
例えばNMCA日本二輪車協会でもそのホームページ上に二輪車駐車場情報を掲載しているが、あくまで自治体などから寄せられた情報を都市ごとに掲載しているものだ。
そういった現状の中、いまNMCAが計画しているのは、ユーザーが出かける前にこれから行く場所を検索すれば、そこにある二輪車駐車場を地図や料金などの情報とともに表示してくれるWebサイト。
これはまた、携帯電話にも対応したものとして考えており、出先にいてもGPS機能で現在地の周辺の駐車場を簡単に検索できる機能を検討しているという。
こうしたサイトができれば、現状でオープンしている二輪車駐車場の利用促進につながることは確か。
今年5月中旬のオープンを目指して準備が進めているとのことだ。
大いに期待したい! そしてそれを活用して、ぜひ二輪車をその駐車スペースに駐めていただきたい!
で、そういうお願いをした上で冒頭見出しに戻る。
二輪車の駐車スペース問題は、二輪車販売店の団体である全国オートバイ協同組合連合会(AJ)の吉田純一会長が「道路スペースに工夫して線を引く」「そして二輪車ユーザーはそれを利用する」—−それで二輪駐車スペース不足問題の多くは解決する、と喝破しているのは以前にも書いた。
そう、そのとおりなのだ。しかし自治体に言わせると、やろうとしても警察がダメと言う、警察は国土交通省(国交省)と意見の相違があると言う、国交省は警察の了解が得られないと言う…。
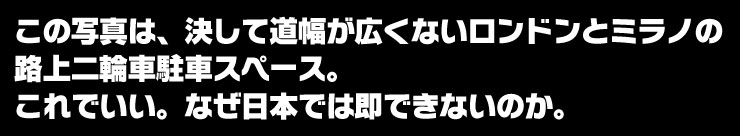


しかし! いみじくもお役人にこう言われたことがある。
「二輪車ってこの社会に本当に必要ですか。不可欠ですか。ユーザーってどれくらいいて、国民のほとんどが、その駐車スペースが整備・新設されることを望んでいる優先事項ですか?」。
「二輪車は本当にこの国で必要とされているか、必要だという提起・発信をしなくてはならない時代になっている」——実は尊敬する二輪設計技術者の大先輩に、こう言われたばかりだ。
トム・クランシーのデビュー作『レッド・オクトーバーを追え』は私にとっても当時、まさに衝撃的小説だった。
実は読売新聞も最近、日本の外交戦略の拙さを語るとき、この小説の一節を引いていた。
その大意は——「サーベルをただ携えているだけのときはガチャガチャと音が出るが、実際に抜くときには音がしないものだ」。
二輪車駐車スペースが不足している、どーするんだ、早くつくれ。そしてようやく行政や社会がサーベルを「ガチャガチャ」言わせ始めたのが今。
しかし、行政もしくはこの世の中・社会が二輪車に「それは優先すべき事項で、国民の多くが望んでいるのか、一部の人のためだけの便宜ではないのか」というサーベルを抜いたら。
しかもその時、前触れの音もしなかったら。
そんな事態はこのコーナーのリードに言う「じじいの放談」か「世迷言」だと言われれば仕方ないのだが…。
これを書いた後、その心配が当たってしまった。
大阪市の担当者が「不要不急の二輪車の利用はできるだけ避けてもらいたい」と新聞取材で発言したのだ(4月1日付・二輪車新聞)。
音もなく“二輪車に普段は乗るな”サーベルが抜かれた瞬間だ。
(2011.04.06更新)
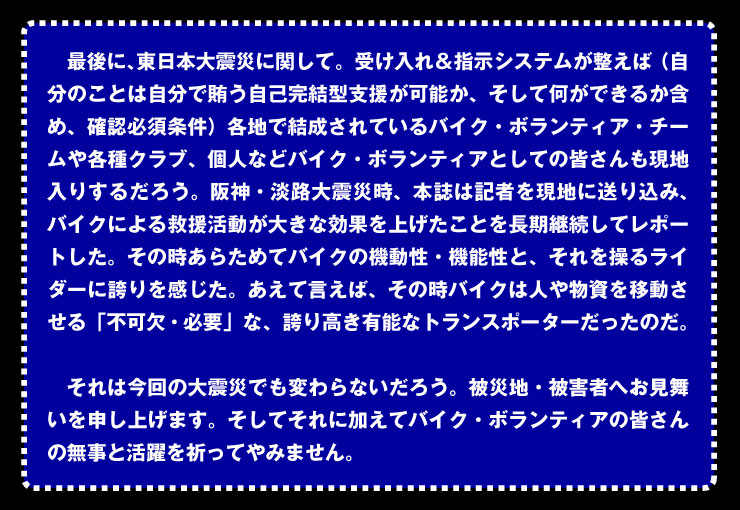
[前のページへ]

