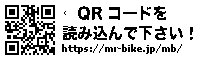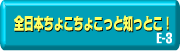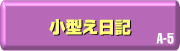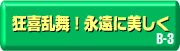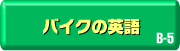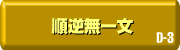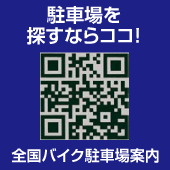|
||
|
|
||
|
西村 章
|
|
スポーツ誌や一般誌、二輪誌はもちろん、マンガ誌や通信社、はては欧州のバイク誌等にも幅広くMotoGP関連記事を寄稿するジャーナリスト。訳書に『バレンティーノ・ロッシ自叙伝』『MotoGPパフォーマンスライディングテクニック』等。第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した『最後の王者 MotoGPライダー・青山博一の軌跡』は小学館から絶賛発売中(1680円)。 twitterアカウントは@akyranishimura |
 |
||
|
フィリップアイランドのレースは、南極方向から吹き寄せる冷たい風や、晴れていたかと思うといきなり凍えるような氷雨が降りはじめる変化の激しい気候が、チームと選手を悩ませる。しかし、今年は三日間を通して晴天に恵まれ、全クラスの全セッションでドライコンディションを維持した。オーストラリアGPで、ここまで気候が温かいのは、この十数年でも非常に珍しいことのような気がする。
“Every rider will be required to enter the pits and change to his second machine with fresh tyres at least once during the race. In normal circumstances this means that the riders must change machine only at the end of lap9 or lap10.”
このように文言上で明示されていることから、マルケスと彼のチームは、11周以上の走行をしてもよい、という解釈はおそらくしていなかったはずだ。していたとすれば、この文章を全く読んでいなかったか、あるいはただの素馬鹿である。つまり、マルケス陣営は本来の11周目を10周目とカウントしていたのではないか、ということが推測される。
もうひとつの可能性としては、ライダーがサインボードをよく見ていなかった、という場合だが、これはマルケス自身がレース後に「<BOX>というサインボード表示があったから入ったけど、そのときはすでに遅かった」と話していることから、これはありえない。マルケスはまた、「チームと話していたのは、10周目に(ピットへ)入ることだった」とも証言している。
‘The team made a mistake, understanding he was able to complete ten laps and come back in before completing lap eleven, and the ‘BOX’ instruction on his pit board was therefore one lap late.’
いずれにせよ、ケアレスミスというにもほどがある稚拙なボーンヘッドで、獲得できていたかもしれない25点を失ってしまうのはあまりに愚かしく、もったいない。とはいえ、マルケスは依然として2013年総合優勝の最有力候補であり、次の日本GPではリザルト次第で史上最年少チャンピオンが誕生する。台風の接近も予測されているだけに、どのような気象条件と路面コンディションになるのか気になるところだ。 |
||

|
||

|
|

|
| 日曜午前のウォームアップでは、圧倒的な乗り換え時間の速さで周囲を圧倒したのだが……。 | ||

|
||
|
ところで、MotoGPクラスの第16戦決勝レースが周回数を大幅に減らし、しかもドライコンディションにもかかわらずフラッグ・トゥ・フラッグという特殊な進行になったのは、今年から路面が新しくなったフィリップアイランドサーキットのグリップがタイヤメーカーの予想を上回るほど非常に良好で、タイヤの発熱が高くなって破損を生じやすくなってしまったため、というのがそもそもの原因だ。MotoGPはフラッグトゥフラッグという既存ルールを今回に限り特別に適用して、レース興業としての面目をなんとか保った格好だが、Moto2クラスは13周に減周し、超スプリントレースとして行われた。あっという間の短い周回数だが、それでもやはり順当に速い選手がきっちりと勝つべくして勝ち、大番狂わせのような事態には至らなかった。
|
||

|
|

|
|

|
| 「王座防衛可能性は2〜3%から、20〜30%くらいにはなった」とレース後に。 |
|
「フラッグトゥフラッグで表彰台を獲得できたのは、今回が初めてだと思う」 |
|
「チャンピオンは難しいが、まだできることはある。次のレースも集中する」 |
 
|
||||

|
|

|
|

|
| 本土からフィリップアイランドにかかる唯一の橋。 |
|
観客動員は三日間総計で7万7200人。 |
|
オーストラリアは、希少種の宝庫なのであります。 |
|
■第16戦 オーストラリアGP 10月20日 フィリップアイランド・サーキット 曇り時々晴 |
|||||||||||||||||
 
|
|||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 1 | #99 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 2 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | HONDA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 3 | #46 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 4 | #35 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 5 | #19 | Alvaro Bautista | Go & Fun Honda Gresini | HONDA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 6 | #38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 7 | #69 | Nicky Hayden | Ducati Team | DUCATI | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 8 | #29 | Andrea Iannone | Pramac Racing Team | DUCATI | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 9 | #4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DUCATI | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 10 | #14 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | ART(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 11 | #41 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 12 | #5 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR-Kawasaki(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 13 | #68 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 14 | #8 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 15 | #9 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 16 | #23 | Luca Scassa | Cardion AB Motoracing | ART(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 17 | #71 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 18 | #70 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM(CRT) |

|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 19 | #52 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 20 | #7 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| 21 | #50 | Damian Cudlin | Paul Bird Motorsport | PBM(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| - | #67 | Bryan Staring | Go & Fun Honda Gresini | FTR-HONDA(CRT) | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
| - | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | |||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
|||||||||||||||||
|
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
[第72回へ|第73回 第16戦|第73回 第17戦へ]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]