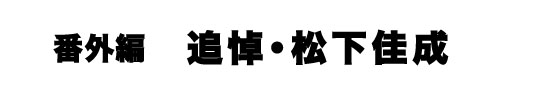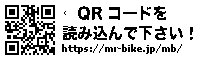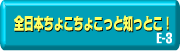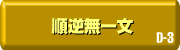自分自身の立場をまずあきらかにしておくと、ぼくは公道レースをスポーツとしてどちらかというと認めたくない、という心情がある。その理由を簡単にまとめると、以下のようになる。
クローズドサーキットで行われるロードレースも、競技の特性上、負傷や生命の危険はつねについて回る。しかし、ルールと施設の整備改善によってそれらの危険性を可能な限り排除し、安全性を最大限に確保していこうとする合理的な精神があり、この考え方が、クローズドサーキットのレースが近代スポーツ競技であることを担保・保証している。
これに対して、公道レースの場合は、負傷や生命の危険は排除可能なものとは考えられていないように思う。どちらかというと、レースに避けることのできない前提条件に類したもののひとつ、と位置づけられているのではないだろうか。骨折や死はコース上の足もとにいつでも平然と転がっていて、そこを走る者が知恵、技術、経験などで対処、回避すべき種類のもの、とでもいえばいいだろうか。であるからこそ、公道レースは完走すること自体が栄誉とされ、走りきった者たちはその勇気を讃えられるのだろう。
この自分の考えを、あるとき、公道レースへの挑戦を続ける松下ヨシナリに対して正直に話したことがある。
「参戦を続けることを、あまり、喜ばしいと思う気になれない」
そういう旨のことを話すと、松下は穏やかな笑みをうかべつつ
「ぼくも、公道レースはモータースポーツだとは思っていませんよ」
とあっさり言った。
「公道レースをスポーツだと考えると、つじつまの合わないことがあまりにたくさんありますもん。あれはむしろ、冒険なんだとぼくは考えています」
そうか、冒険なのか。そのことばを聞いて、なぜ彼が公道レースに魅力を感じ、挑戦を続けようとするのか、すとんと腑に落ちたような気がした。公道レースを走ることは、登山や極地に挑むことと彼のなかではおそらく同義なのだ。
「冒険である以上、最後は安全に戻ってこなければいけない。ただの無謀な行為をやっているわけじゃないんだから。生きて帰ってきてはじめて、冒険が成立する。死んじゃあ、ダメなんです」
そこにまったく、異論はない。向こう見ずな思いきりが結果を左右するのなら、それはただの蛮行にすぎない。一見したところ外野からは、ぎりぎりの淵に生命を賭す環境へ身を投じているようにしか見えないとしても、じっさいの当事者自身は最大限の安全を自分のなかで確保しながら目標を達成し、戻ってくる。冒険とは、そういうものだろう。
冬期単独無酸素登頂に挑む友人を見送るのと同じことなのだ。そう考えれば、彼の挑戦を自分のなかで納得することができた。
そして、その連想から、登山家の山野井泰史氏が著書『垂直の記憶』で言及していた、山で死んでも非難してほしくない、という一節をおぼろげな記憶で話すと、しかしこのとき松下は彼の主張に猛反発した。
「死ぬことが許される権利なんて、ないですよ。オレはそれは絶対に違う、っていいたいですね。非難しますよ。絶対に生きて帰ってこなきゃ、意味がない」
正確を期すために、少し長くなるがその一節を以下に引用しておこう。
<かりに僕が山で、どんな悲惨な死に方をしても、決して悲しんでほしくないし、また非難してもらいたくもない。登山家は、山で死んではいけないような風潮があるが、山で死んでよい人間もいる。そのうちの一人が、多分、僕だと思う。これは僕に許された最高の贅沢かもしれない。
僕だって長く生きていたい。友人と会話したり、映画を見たり、おいしいものを食べたりしたい。こうして平凡に生きていても幸せを感じられるかもしれないが、しかし、いつかは満足できなくなるだろう。
ある日、突然、山での死が訪れるかもしれない。それについて、僕は覚悟ができている。
『垂直の記憶』(P165-166)>
こうやって改めて正確に引用してみると、山野井氏の言に松下が反発した理由がよくわかるような気もする。
<ある日、突然、公道レースでの死が訪れるかもしれない>ということに関しては、松下もおそらく、あくまでも可能性のひとつとして理解をしてはいただろう。
だが、<それについて、僕は覚悟ができてい>たのかというと、これにかぎっては、けっしてそんなことはないはずだ。彼は、その死を回避しながら確実にレースを終えて戻ってくるつもりだった。
絶対に。
それこそが「冒険」なのだから。
しかし、最後のマン島になるはずだった今回の挑戦で、松下ヨシナリはその冒険を完遂することができなかった。そのことが、ただただひたすらに、残念だ。
松下佳成選手のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
2013年5月28日 記